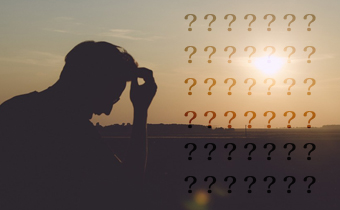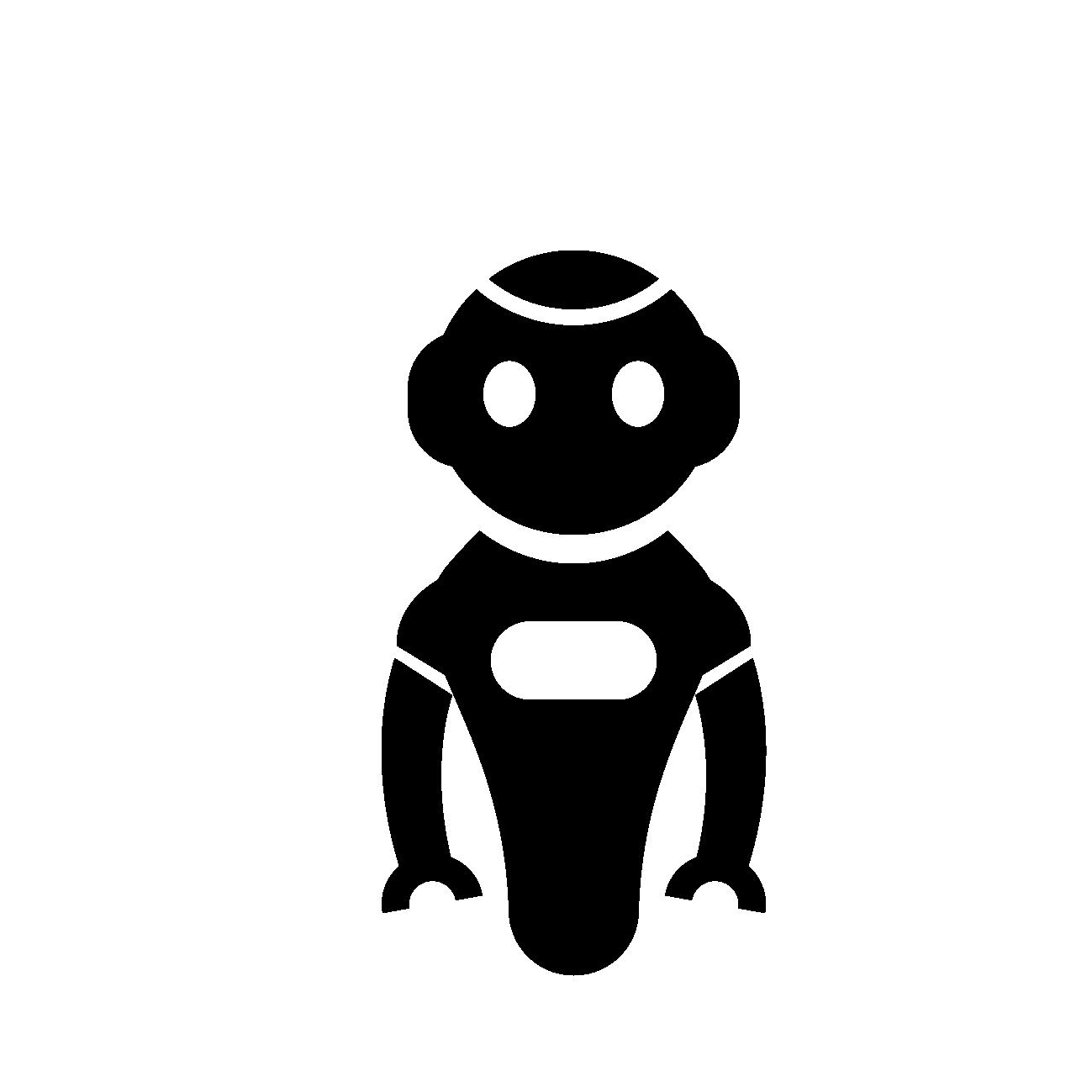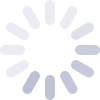
Knocknote
OURSELVES
会社概要
| 社名 | 株式会社Knocknote (カブシキガイシャ ノックノート) |
| 設立日 | 2017年1月 |
| 決算月 | 12月 |
| 役員 | 代表取締役 鈴木 道生 |
| 本社所在地 | 〒160-0007 東京都新宿区荒木町9-7 ナオビル 2F |
| 事業内容 |
|
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 四谷支店 ジャパンネット銀行 |
| 電話番号 | 03-6709-8725 |
| FAX番号 | 03-6709-8726 |
| メールアドレス | info@knocknote.jp |
代表メッセージ
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
私たちKnocknoteでは「夢で満ち溢れた明るい未来を」という経営理念を掲げ、プログラミング教室、システム開発、ICT・IoTソリューション事業を行ってまいります。
今後は、社会や子供たちの未来に貢献する企業となるべく、邁進してゆく所存です。
何卒皆様の格別のご支援を賜りますようお願い申し上げます。
代表取締役 鈴木道生